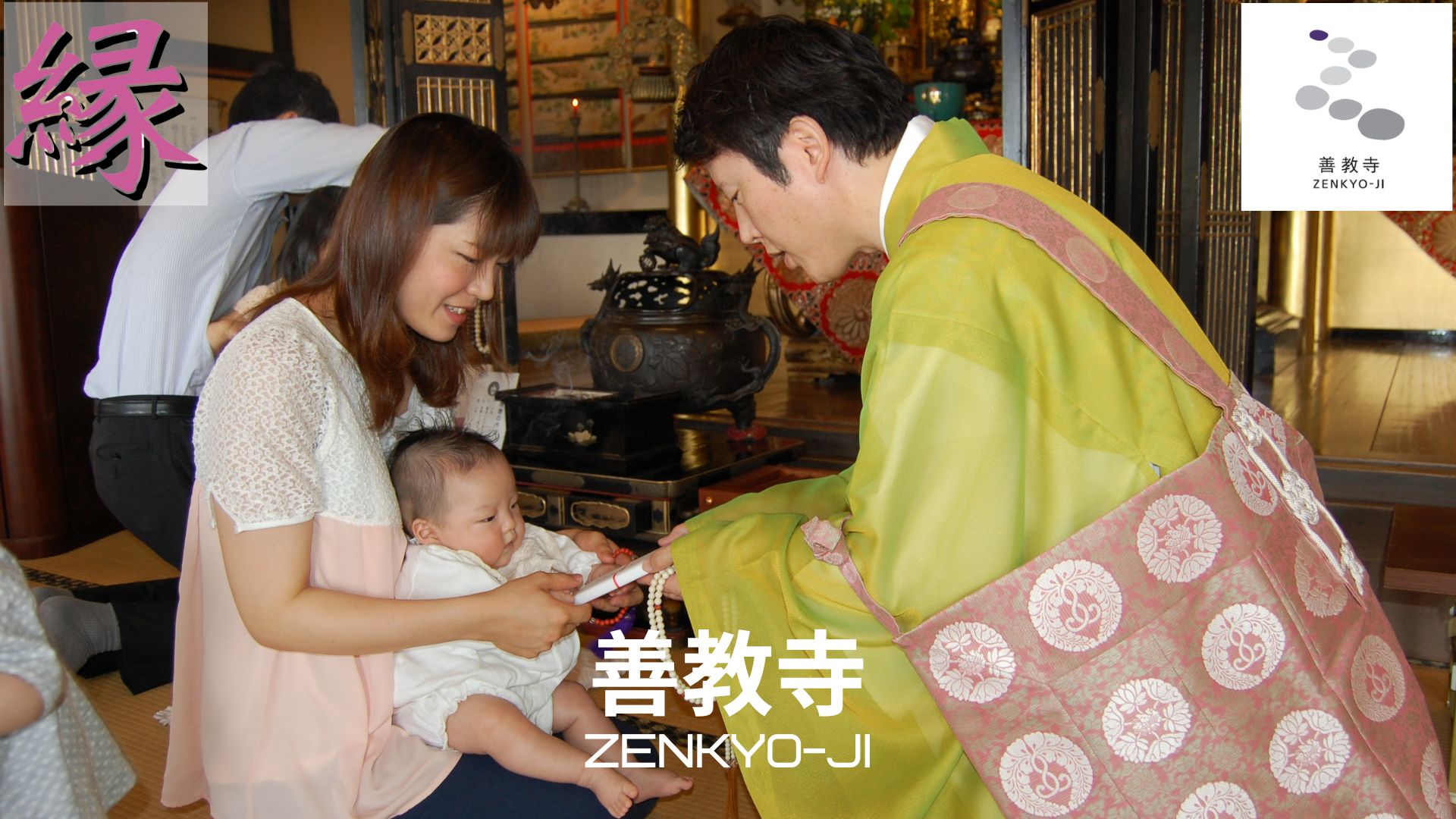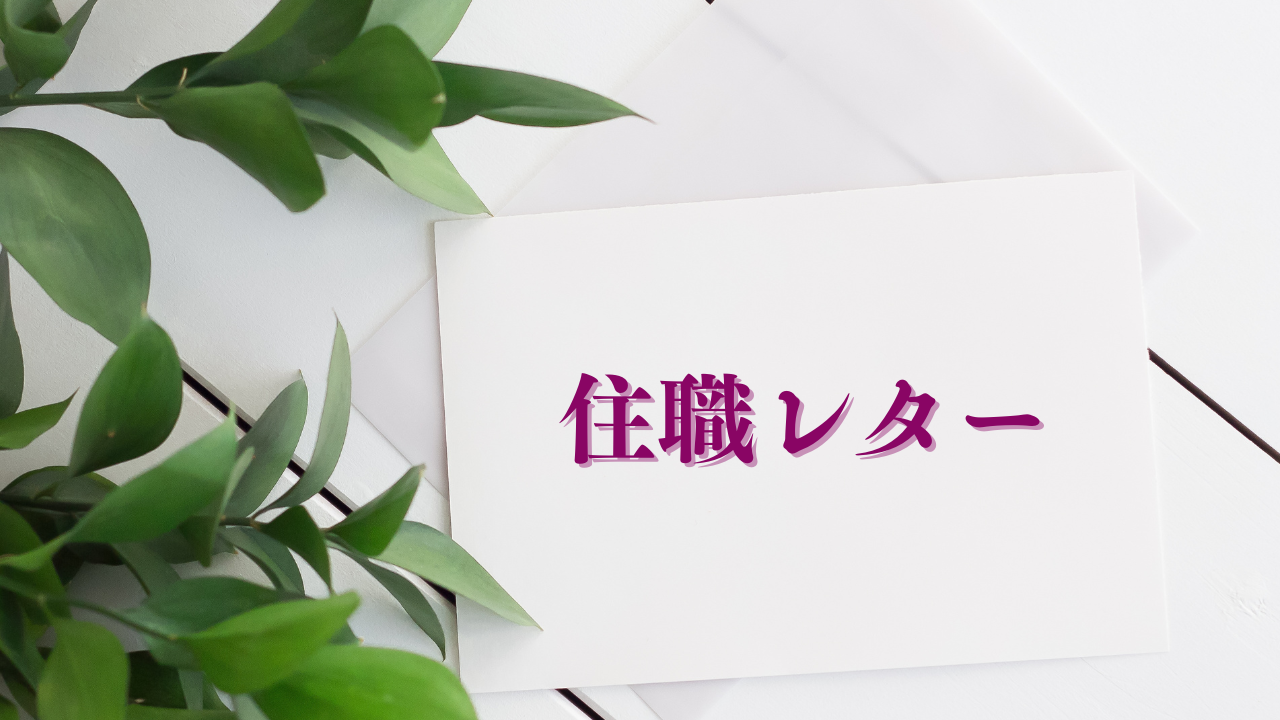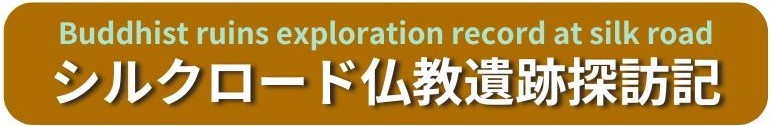
| 7月 |
先月の住職レターで、『物には魂が宿っている』という話をしました。私自身が、改めて大切な事に気付きを得ることが出来たのか、父の使っていた念珠を手にすると父を思い出し、節折(せったく)を手にした時には、会ったことのない先祖にまで、思いを馳せました。
私がいつも法事に参勤して、仏説阿弥陀経を称える時に使っている節折、せったくと読みます、一般的には拍子木と言われますが、かなり古い物(仏具)、らしいです。
三十年前、私が住職になって、初めてこの節折を手にした時、祖母が、「おじいちゃんも使っていたんよ」と言ってました。私が、「いつから使っとるん?」と聞くと、「おじいちゃんのおじいちゃんが使っとったらしい」とのこと。という事は、少なくとも、この節折は、五代前から使い続けているようです。一代を約三十年として、最低でも百五十年が経過。どうりで、打ち付ける箇所が、削れている筈だと納得しました。同時に、歴代住職が使っていた、この節折が重たく感じてきました。歴史の重みってことでしょうか。
法事にお参りする方の仏間に、火鉢が置いてあります。今は使われていません。私が見る限り、ただの古い物でした。ある時、その家の方が、この火鉢は、亡くなった親父が大切にしていた、いつも火鉢に身を屈めて手を温めたり、酒を燗したり、するめを焼いていた。火鉢を見るたびに、亡くなった親父を思い出すと、話して下さいました。
こんな話を聞いてから、その方の家の火鉢が、ただの古い物ではなく、魂が宿ったように感じました。

| 6月 |
『物(もの)』には命はありません。しかし、物に魂が宿る瞬間を感じたことはありませんか?
例えば、その物を見たら、懐かしい人を思い出した、その物に触れたら、大切な人のぬくもりが感じられてくるとか。
この時期、いつも衣替えをします。御衣箪笥の中から、何年も着ていなかった古い御衣を手に取ってみました。明らかに、昨年までの御衣よりも、着丈が長い。「はて?」、直ぐに分かりました。「おじいちゃんが着ていた衣だ」、その瞬間、その御衣に魂が宿りました。大好きだった祖父を思い返し、御衣を身に着けたら、おじいちゃんが優しく抱きかかえてくれるような、安心感に包まれました。
本堂の香炉を磨く時、獅子と龍に挨拶します。すると、獅子と龍に魂が宿るが如く、優しく微笑み掛けてくれるような気がしてきます。
昔は、物を大事に使い、大切にしてきました。それは、物には魂が宿っていると感じていたのでしょう。今の私たちは、物は使い捨て、直ぐに新しく買う。
物に命を感じること、今の私たちには必要な価値観のような気がします。
何か一つでも、自分の魂を宿した物を、次の世に残せたら良いですね。


| 5月 |
以前のコロナ禍においては、人と距離を取るのは当たり前、ひどい時は、人と会うことが憚れていました。会社においては、オンラインミーティングが普通となり、飲み会はご法度でありました。コロナ禍の数年で、人と触れ合うことが少なくなったように思います。そのせいで、世の中の価値観が大きく変化しました。
お寺では、家族葬が普通となり、従来型の、近所や職場の方が参列する、一般葬は激減しました。葬儀後の、四十九日法要・一周忌の法事等々においても、少人数での法要が続きます。寺の本堂での各種法要も、参拝者が減りました。
先日(四月二十日)、仏教婦人会役員会を、善教寺庫裏にて開催しました。忙しい中、各自の予定をやりくりして、出席して下さった役員の皆さまから、「人と会えるのは嬉しい」「楽しみにしている」「学ぶことが多い」と、有り難い事を言って頂きました。
このように、仏教婦人会の役員の皆さまが、人と会うことの大切さ、触れ合うことの喜びを、口々に発して下さるのは、住職冥利に尽きる思いであります。
仏教婦人会の役員の皆さま、頼りにしてますよ。いつも有り難うございます。


| 4月 |
三月七日の昼席~八日の朝席と昼席にて、善教寺仏教婦人会報恩講と総会、無事に勤め終えることが出来ました。法要のご講師は、光明寺(奈良県)の三浦真証先生。実は、三浦先生には、来年も来て頂きます。
来年は、東広島組仏教婦人会連盟大会を、善教寺で法要開催しなくてはなりません。東広島には浄土真宗寺院が二十二寺あり、各寺で持ち回り開催しております。ゆえに、二十二年に一度、この法要開催を引き受けることになります。
令和八年度、東広島組仏教婦人会連盟大会の記念法要講師として、三浦真証先生に来て頂くことになりました。
開催日は、来年(令和八年)六月六日(土曜日)ですから、今からご予定ください。
二十二年前の前回、準備が大変だったことが、今でも思い返されます。東広島組仏教婦人会連盟の役員さんを中心に運営され、献花・献灯・献香の予行演習から司会進行の練習、何度も善教寺へ集合して、打ち合わせを重ねました。そして一番大変だったのは、協賛広告集め。近隣で会社経営されている業者、店舗、酒屋を廻って、協賛広告のお願い行脚をしました。当時の私は、まだ若かったせいか、これが大変な苦痛で。人様からお金を頂戴するのが、これほど大変な事なのかと、身をもって知り得た、とても貴重な体験でありました。
今は、協賛広告集めも無くなり、各寺の負担はかなり軽減されたようです。法要を開催するには、大変な気苦労も多いかと思いますが、善教寺仏教婦人会役員の皆さんと一緒に、良き思い出が作れるよう、今から楽しみにしています。


| 3月 |
この時期は、総会開催が続きます。主なのは、善教寺護持会総会と善教寺仏教婦人会総会。護持会は、毎年二月十一日に開催。仏教婦人会は、来月(三月)の八日、報恩講法要の日に開催します。
護持会総会には、今年も多くの善教寺世話係が出席して下さいました。護持会の石原会長の挨拶では、時代の変化に応じた寺院運営の必要性と、そして善教寺がこの地に開基したのは、西暦一五一三年(室町時代中期)であると言われ、五百年以上の歴史ある、我々の寺を、これからも皆で護っていきましょうと、有り難い話をされました。
昨年度の行事報告と会計報告、来年度の案も承認され、無事に護持会総会を終えました。
総会には、普段の法要にはお参りされない方も、多く出席して下さり、その皆さまとお話をさせて貰える事は、とても有り難いです。
庫裏での懇親会では、お酒も入ったせいか、いろいろ本音で語り合って下さいました。皆さん、善教寺の事を心から思って頂き、また住職としての私を応援して下さっていることが改めて分かり、私自身が元気を貰えた、護持会総会でした。




| 2月 |
一月十一日(土曜日)、無事に御正忌法要を勤め終えたのですが、実は朝から、トラブル続きでした。法要日前後の厳しい冷え込みが影響したのか、台所のお湯が出ない。給湯器の凍結防止処置はしていたので、問題ないはず。門信徒会館の給湯器の電池を交換するも反応なし。困り果て、約一時間後に再度試みると、ようやくお湯が出て事なきを得ました。
問題はそれだけでなく、庫裏の大台所の給湯器からもお湯が出ない。こちらの給湯器は業務用なので、ガス会社に来て貰いました。寒さのせいか、給湯器の性能が落ちているとのこと。取り合えず、当日の法要で使えるように応急処置をしてもらいました。ガス会社の方が、「給湯器を設置して二十七年経ってます。交換部品も無いので、そろそろ新しい給湯器に替えられた方が・・・」と。
給湯器の寿命は、約三十年でしょうか。パソコンやスマホは、四~五年、長く使ったとしても七~八年。冷蔵庫や洗濯機は、十年~二十年か。本堂にある仏具の寿命は、よく分かりませんが、最低でも百年、中には、二百~三百年使い続けているのもあるでしょう。
一方、浄土真宗が開宗されて、八百年超、正確には一昨年、立教開宗八百年慶讃法要が勤められましたので、八百二年になります。
御正忌法要は宗祖親鸞聖人の祥月命日のお勤めです。八百年続く大切な法要に心血注いで集中しなくてはなりませんが、それ以上に、三十年使い続ける給湯器の事に、心が向いてしまい、煩悩だらけの私を反省し、御正忌法要を終えました。


『給湯器のお陰で法要料理が作れています』
| 1月 |
年末を迎え、慌ただしくされていることでしょう。大掃除、年末の挨拶周り、年賀状の作成。そして私には、最後に大仕事があります。除夜会法要の読経と、除夜の鐘つき。除夜の鐘は、大晦日の深夜0時をはさんでつく鐘のこと。ちょうど日付けが変わり、新しい年になる時を鐘をつきながら迎えます。
人には百八つの煩悩があると言われ、その煩悩を滅するために、除夜の鐘を百八回つきます。煩悩とは、人の心を惑わせたり、悩ませ苦しめたりする心のはたらきのこと。代表的な煩悩は、一.欲望、二.怒り、三.執着、四.猜疑。
なぜ煩悩の数は百八つとされているのかは、諸説あります。百八という数が、『沢山』という意味だというのが、一般的でしょうか。
私がなるほどと思った説は、人間が持つ欲望や心の汚れは、六つの感覚器官(眼・耳・舌・鼻・身・意)からもたらされ、それらが感じとる感覚からくる三十六個の煩悩に、前世、今世、来世の三つの時間軸をかけて、百八つあるという考え方。ようするに、私たちの煩悩は、たくさんあって、際限ないといことでしょう。
あまり知られていませんが、梵鐘の鐘の回り(上部)に突起があります。これは「乳(ち)」と言われるもの。この「乳」の数も百八つあります。
古より、梵鐘の鐘の音そのものには、苦しみや悩みを断ち切る力が宿っていると考えられてきました。梵鐘の澄んだ音は、深夜の空気と相まって心にしみわたり、私たちの魂が共鳴するような気持ちにさえなります。
除夜の鐘、つきに来て下さいね。

建立s-rotated.jpg)