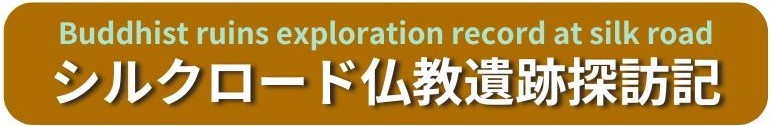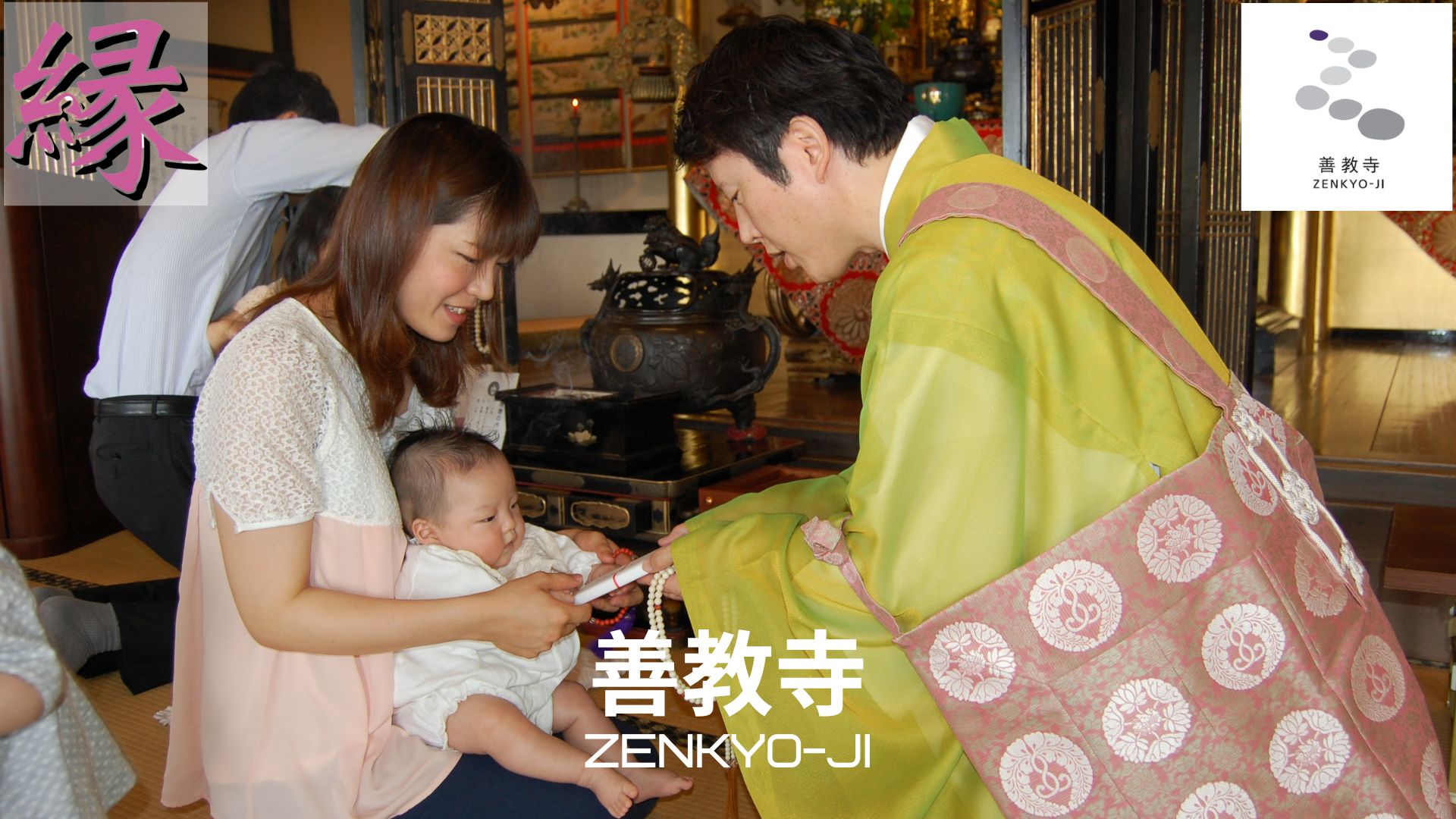西安のホテルには、朝食にパンがあった。しかしここ宝鶏では朝から中華ビュッフェ。私は食に関して好き嫌いはなく、何でも食べられると自負していたが、さすがに毎日の中華料理には辟易し、食べるのが嫌になる。今朝は、中華粥を軽めに、お腹に入れた。
これから、西に行くとイスラム料理圏内に入り、羊肉が主食になる。羊肉が苦手な私は、今後益々頭を痛めそうだ。
今日は宝鶏市内観光に行った。ホテルの旅行会社に、観光ガイドブックを指して、「ここと、ここに行きたい」「日本語通訳はいるか?」「タクシーをチャーターしたらいくらか?」等を、筆談を交えて交渉した。
宝鶏は西安に次ぐ陜西省第二の都市、人口は30数万人を超えている。しかし日本人を含め、観光客があまり来ないそうだ。決まった観光ツアーはなく、自分でアレンジして交渉するとのこと。ホテルの旅行会社なら、騙される事は無いかと思ったが、それでも交渉には疲れた。
三国志を愛読していた私は、以前から宝鶏の古大散関に行きたいと思っていた。ここは周囲の地形が険しく、麓と山頂の高低差が1000メートルに及ぶという交通の要所。四大関所の一つで、三国志で有名な劉備玄徳が建国した蜀への道の難所として有名である。古来より兵家必争の地であった。



三国志の英雄の一人、曹操が諸葛亮孔明とここ古大散関で争っている。今回は残念ながら行けなかったが、諸葛亮孔明が出帥表を奉って出陣し、死んでなお後に「死せる孔明、生ける仲達(魏軍の大将・司馬懿のこと)を走らす」と言われる、有名な合戦場である五丈原、そして諸葛廟もこの宝鶏の南にある。
項羽と劉邦もここ古大散関に来ている。それを思うと胸が高鳴った。当時の武将が感じたことを体感しようと思い、観光ガイドと一緒に高台まで歩いた。およそ20分くらい、楽ではなかった。この辺りの高台から曹操も戦況を見つめていたかと思うと、感無量だった。観光客が来ない宝鶏に敢えて立ち寄っただけのことはあった。
その後、道教の宗教施設である金台観、中華民族の祖先とされる炎帝を祀った御堂へ行った。
また宝鶏は、古代周文明(約三千年前)の中心地で、多くの遺跡が発掘され、青銅器が多数出土している。その出土品を沢山展示してある青銅器博物館へも行った。
夕方ホテルに帰り、明日の出発準備に取り掛かった。鉄道で約3時間の移動である。チケットはホテルの旅行会社に依頼しておいた。外国人観光客用の『軟座』シートが取れたので、昨日より楽な移動が出来ると思う。

・観光ガイドの馬さん(右)s.jpg)